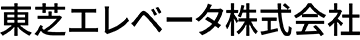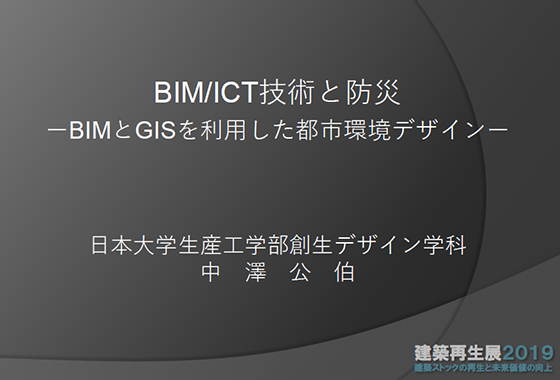第24回R&R建築再生展2019:トークセッション 1
BIM/ICT技術と防災
東芝エレベータは「建築ビジネスの最適化・効率化を推進 働き方を変える。東芝エレベータが変える」をテーマに掲げ、2019年6月11日~13日に東京ビッグサイト青海展示棟で開かれた「第24回R&R建築再生展2019」に出展しました。
建築再生展では、IoTやBIMを活用して建築業界の利便性向上と効率化を実現するサービスに関する展示を行うとともに、12日、13日には6人の外部有識者を招いてセミナーとトークセッションを開催しました。
今回は6月12日のトークセッションをご紹介します。


- 山田 悟史 氏
- 立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科 任期制講師
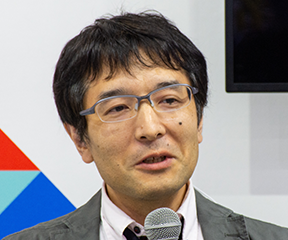
- 中澤 公伯 氏
- 日本大学 生産工学部 創生デザイン学科 教授

- 長坂 俊成 氏
- 立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科 教授
トークセッション 1
BIM/ICT技術と防災
BIMデータをGIS(地理情報システム)などの他のICT技術と組み合わせて活用することで、
避難シミュレーション、環境シミュレーションなど、防災分野に活かすことができます。
BIM/ICT技術の防災分野における可能性について、3名の有識者の方々に議論していただきました。

中澤 公伯氏
日本大学 生産工学部 創生デザイン学科 教授
長坂 俊成氏
立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科 教授
山田 悟史氏
立命館大学 理工学部 建築都市デザイン学科 任期制講師
長坂:
皆さん、こんにちは。最初に、お二人の先生にそれぞれの研究紹介をしていただいて、その後にディスカッションを進めていきたいと思います。
山田:
立命館大学の山田です。僕の専門は、コンピューターを活用して建築や都市を計画する「建築情報」という分野です。授業はCADやCG、BIMを担当しています。研究では、セミナーで紹介させていただく、AI(人工知能)やVRなどの先端技術への挑戦と並行して、防災に関するシミュレーションや数理計画を使った研究も行っています。
その中のひとつに、局地的豪雨により京都の地下街に浸水が生じた際の被害予測と対策立案を避難シミュレーションにより行う研究があります。
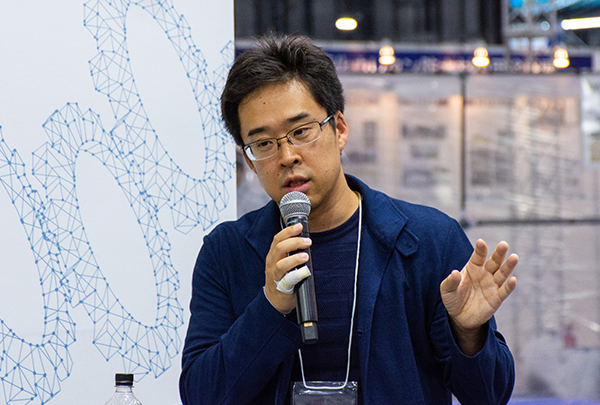
この研究では、お客さん、駅員さんなどの役割を担う「エージェント(小さなAI)」をたくさん作ることで人の動きを観測するマルチエージェントシミュレーションという技術を使いました。この際にインフラのデータも含め BIMデータを入手できれば、と強く感じました。エージェントが行動する空間の設定に使えるからです。地盤面の透水量、排水溝や排水管の性能、地下出入り口の幅やマウントアップの高さなどは被害にクリティカルです。また、地下街の駅や通路、店舗の排水能力も被害にクリティカルです。このような感度の高い設定に限らずこの種のシミュレーションでは、安易に「安全である」という結果を導かないように注意します。もちろん調査による設定を試行しますが、不確かさが強い項目は危険側に設定します。そのため、過大な被害を予測してしまうこともあります。研究としては間違いではないと思う一方で、立案した対策が実現困難な内容になることもあり、知見としてこれが有用なのか、と悩むこともあります。インフラも含めたBIMデータが、オープンとまではいかなくても、ワンストップで利用可能になれば、実行力のある研究や提案を促進できると思います。
このような思いは、ある自治体の依頼で行った津波避難計画でも感じました。大規模災害に備える津波避難ビル・外部階段・避難経路をどのように計画したら住民の平均避難時間が最短になるのか、どこにいくつ計画したら津波に巻き込まれてしまうと予測される人を0人にできるのか、を数理的に検討した研究です。結果にクリティカルな項目には、倒壊危険性の高い建物、被害を受ける可能性の高い橋などの道路閉塞の可能性が挙げられます。これらについてもインフラを含むBIMデータが利用できれば、より実行力のある研究ができたのではないかと思っています。
長坂:
今の視点はすごく大事で、都市モデルのビッグデータと建物のBIMデータを使ってシミュレーションしないと、リアリティのある結果がなかなか出てこないというご指摘です。平常時の建物の状況とライフラインの被害想定、リアルタイムで収集された被害状況の情報を組み合わせることで、災害時の応急対応が可能になります。そのためには、都市計画、土木、建築など多様な分野の方々と様々なビッグデータを共有することが、今後必要になるのではないかと思っています。

中澤:
日本大学の中澤です。BIMとGISの連携についてお話しします。
BIMは、簡単にいえば3次元CAD+データベースです。このBIMの利用先を、環境シミュレーションや社会情報・ニーズ発見、防災・減災まで広げるには、3次元データの広域化、複数パターン化が必要になってきます。
広域化するには、どうしてもGISと連携させる必要があります。GISは地理空間情報、BIMは3次元CADといったように、扱っているオブジェクトこそ異なっていますが、システムの部分は非常によく似ているので、私は両者を連携できるのではないかと考えました。
連携するためには、インターネット上に大量にある2Dの空間情報を活用するのですが、2DのままではBIMモデルに取り込めないので、3D化します。
また、複数パターン化を行うためには、VAE※1のプログラミングの力を活用します。具体的な事例として、日照と風況を考慮した環境シミュレーションを紹介します。
以上のお話を整理すると、BIMの利用先を環境シミュレーションや社会情報・ニーズ発見、防災・減災まで広げるには、広域化と複数パターン化が必要であり、それらはGISとの連携とVAEによるプログラミングを活用すれば可能になってくるということです。
長坂:
長年、地理空間情報は2次元止まりでしたが、ようやく3次元のBIMの本格的な利用が可能となりました。中澤先生の話をお聞きしていると、BIMを使えば、3次元かつ広域のシミュレーションが可能になり、今、ようやくその世界の入口に立った段階かなと思いました。
これまでの話をお聞きしていると、お二人の共通の問題として、BIMの活用により、どこまでシミュレーションの精度が高まり、問題解決に資するかということがありますので、それについてコメントをいただけますか?

山田:
シミュレーションはクリティカルな設定の読解や探索が肝要ですので再現精度は深遠な課題です。ただBIMという多次元データは、形態に関する3次元情報だけでなく「これがあれば、もっといい研究ができるのに」というデータを結構持っています。形態に関する情報だけでなく、データベースにこそ有用な情報が多いと思います。僕は研究したことがありませんが、エネルギー分野はわかりやすい例かと思います。防災に関連させて少し珍しい例を僕の研究から紹介すると、AED(自動体外式除細動器)の配置検討シミュレーションがあります。この際、AEDの利用可能時間が問題となりました。AEDの位置座標と並行して使用可能な状態にあるか確認すると様々でした。「ビルが開いている時間内」という事例だけでなく、「回答できない」という事例もありました。研究は対象空間を他から独立した抽象空間に置き換えられるケースでしたので大きな問題になりませんでしたが、時間という次元が結果にクリティカルになる事例も多いと思います。都市部は意外とAEDが設置されているのですが、時間帯によっては善意ある一般市民がAED処置を試みても近くのビルにあるAEDが使えない、という可能性です。このようなことを踏まえた計画と運用にもBIMがもつ多次元データは有用です。建築物を設計するという意味では、AEDの有無や数と位置、利用可能時間は付帯的な情報かもしれませんが、救急救命という分野では計画と運用に非常にクリティカルな次元ということです。
このように、何をシミュレーションするかによって必要なデータベースの次元(項目)は変わり、ある分野ではさほど重要でなくても別の分野では価値がある、という次元も多々あると思います。各次元にどんな利点があるかを理解・共有して、オープンでなくてもワンストップで利用可能な仕組みでデータベースを多次元化していくことが大切だと思います。またあらかじめ利点がわからなくても、業務の過程で作成された次元はとりあえず足して多次元化した情報を分野横断的にどこかが管理しておく、ということも必要だと思います。
中澤:
精度の問題にからめていえば、現時点でBIMのデータは、現実世界とまだそれほどリンクされていない点も大きいですよね。データ作成後の活用先も考慮しながらBIMデータを作る方向に舵を切れば、現実世界とは今後どんどんリンクしていくのではないかと考えます。

長坂:
精度には、位置精度、時間的精度以外に、論理的精度があります。論理的精度とは、例えば道案内をする時、道路を挟んで右か左か、「次の交差点のコンビニの向かいです」といった具合に、事物の相対的な位置関係から場所を特定できるということです。つまり、精度を高めなければデータが利用できないということではないと思います。
もう1点、BIMデータの公開・標準化の現状と今後についてはいかがでしょうか?
中澤:
現実によく聞く話では、ゼネコンさんが設計する際、設計用BIMと施工用BIMでデータが異なるという問題があり、公開できるようになるのは少し先という認識を持っています。データ形式の標準化も現在進められている段階で、誰でもデータを見られるようになるのはまだ先ではないかと思います。
山田:
僕も、標準化は現段階ではできていないという認識です。ただ、buildingSMART Japan※2でIFCフォーマット※3などの標準仕様を決めるという動きはあります。異なる会社の連携を意図したコミュニティです。このコミュニティに限らず、研究者、もしくは技術者個人レベルでは、連携してこの分野を発展させようという意思が高まっている印象です。会社同士の連携には伺い知れない難しさがあるとは思うのですが、直近の利益をいったん保留できるような力を持っている会社が率先して連携し、標準化を進めて業界をリードしてくれたらいいな、というのが大学研究者の思いです。
長坂:
データの公開に際して、セキュリティ、知的財産権などの問題がありますので、非常に難しいと思います。しかし、目的に応じてレイヤーを分け、一部のレイヤーを公開していただけるようになると、様々なシミュレーションに活用できるようになり、社会的に防災性や環境性能を高めることができます。安全・安心な社会を実現するために、建築業界の方々には、是非頑張っていただきたいと思っています。
本日は、長時間にわたり、ありがとうございました。
※1 VAE:RevitのアドインソフトであるVisual Algorithmic Editor「Dynamo」のこと。
※2 buildingSMART Japan:IFCの策定・普及活動を行っている団体。 https://www.building-smart.or.jp/
※3 IFCフォーマット:BIMソフトウェア間の相互運用性を高めるために、buildingSMART Internationalが開発および維持しているフォーマット。
次回はシリーズインタビュー「ICT技術とBIM」の第2弾として
小松平佳氏(AI-feed代表取締役)&金田充弘氏(AI-feed取締役)が登場!