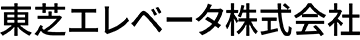シリーズレポート「BIMが切り開く未来の街」 第1部 vol.2
設計・施工・生産を
デジタルでシームレスにつなぐ
- 第1部 vol.01
BIM着工100%に向けて - 第1部 vol.02
設計・施工・生産をデジタルでシームレスにつなぐ - 第1部 vol.03
ICT技術が切り開く
「暮らし」の未来形 - 第2部
築地市場跡地の
新たな可能性

前回は、長谷工コーポレーション(以下、長谷工)のBIMの特徴をはじめ、
長谷工がBIMを導入する過程でどんな課題に直面したのか、
これらの課題をどのように解決したのかを中心にお伺いしました。
第1部の2回目では、ICT技術の導入で変貌する建設業界の姿にまで話題を広げ、
長谷工がデジタル化された図面やAIを施工・設計にどう活用しているのか、
さらには、何を目指し、どのようなことに取り組もうとしているのかについてもお伺いしていきます。

原 英文さん
株式会社長谷工コーポレーション
建設部門 建設BIM推進部 部長

中野 達也さん
株式会社長谷工コーポレーション
エンジニアリング事業部 BIM推進室 チーフ

稲垣 拓さん
itaru/taku/COL. ファウンダー
https://www.itarutakucol.com/
(モデレーター)

中島 貴春さん
株式会社フォトラクション
代表取締役 CEO
https://www.photoruction.com/corp/

石原 隆裕さん
シンテグレート
http://www.syntegrate.build/ja/home
デジタルデータの活用、ペーパーレスを推進する施工分野
稲垣:
ICT技術は今後、建設業界を変えていくといわれています。前回はBIMに関する話を中心にお伺いしましたが、第2回目ではICT技術を取り入れた具体的な取り組みについてお伺いできればと思います。
中野:
施工部門にはたくさん事例がありますね。
原:
設計図書のデジタル化が進んできたので、それを施工側で活用する取り組みがいくつも行われています。そのひとつに、Rebro※1で描いた設備図を用いた風量測定の効率化が挙げられます。SpiderPlus※2というアプリを活用し、設備図をタップするとBluetooth接続の風量測定器が測定を開始するのですが、これによりデータ収集から整理・集計までにかかる時間が、これまでの4分の1程度に短縮できました。また、精度の高い位置合わせをするのに、現場では自動追従レーザー墨出し器を使っているのですが、そのもとになる点データは、Point Layout※3というソフトを使って、BIMモデルから作成しています。
ほかには、現場の業務から紙を全部なくそうという取り組みも進んでいて、各種書類はタブレット上で直接作成できるようにしました。デジタルデータが蓄積され、ビッグデータになったら、中島さんの会社の「aoz cloud」を使えるので、今はその準備をしている段階(笑)。


ICTの活用で進む施工現場の省力化。写真は配筋検査の記録をタブレットに入力している様子
出典:長谷工コーポレーション
中島:
ありがとうございます(笑)。
原:
施工分野は、過去の蓄積がデジタルデータとしてあまり揃っておらず、AIを適用するのが難しい状況にあるんですよね。近い将来、AIや様々な分析にデータを使えるようにするために、今はどんな情報でもデジタル化して蓄積している最中ですね。

石原:
何でもデジタル化すると、現場から反発が出てくるのではないでしょうか?
原:
昔ながらのやり方の人がいるので、当然、反発する人は出てきますが、今現在20代の社員が40代になった時に、能力をフルに発揮できる環境を今から作っているのだと説明しています。また、3回以上タップが必要なソフトだと現場では使ってもらえないので、1〜2回のタップで入力が完了するように気を配りました。
稲垣:
インターフェースはソフトの中身と同じぐらい重要ですからね。
※1 Rebro:NYKシステムズが開発した建築設備専用CADソフトで、BIMツールとの連携に優れる。
※2 SpiderPlus:レゴリスが開発した建設・メンテナンス業向け図面、現場管理アプリ。Rebroから風量測定検査箇所のデータを取り込み、計測データをRebroに戻すことができる。
※3 Point Layout:Autodesk社が開発した建設現場のレイアウト構築ソフト。
AIによる自動チェックで省力化を目指す設計分野
中野:
設計部門では、AIを使ったBIMモデルの自動チェックに現在チャレンジしているところです。弊社では、設計、施工など様々な立場の人間が、安全性、防水性能、仕様、施工計画、使いやすさ、管理しやすさなど多角的な視点からBIMモデルをチェックしています。チェック項目は、1案件あたり300〜400ぐらいです。そして、モデルデータを修正したら、修正前後のデータが両方保存されるのですが、これを教師データにして、AIによるチェックツールを開発できないかと考えたのです。「ここは異常箇所の可能性がある」とレコメンドしてくれるツールをイメージしています。

現在の設計図書モデルチェックの様子。右上にチェック項目がリストアップされ、各項目をダブルクリックすると当該箇所にジャンプする
出典:長谷工コーポレーション
稲垣:
チェック作業は、労力や時間を要する割に、内容としては単純なものが多いので、AIでできるのではないかということですね。

中野:
そうです。市販されている干渉チェックソフトは、決めたルールの中でしかチェックしてくれませんし、モデルの作り方の変更などに合わせ、ルールをメンテナンスし続けなければなりませんからね。
石原:
ルールベースの干渉チェックソフトの場合、項目が出過ぎる傾向がありますし、逆に予想外のものが漏れたりすることもあるので、最後は人間の目に頼らざるをえません。機械学習を使って自動化が進められると、労力は大きく減らせますね。
中島:
弊社では、人の作業をAIで自動化する案件がいくつも動いているのですが、業務フローに当てはめてみると、実は難しかったという案件が結構多いです。例えば、戸建てが法に適合しているかどうかをAIにチェックさせ、最終的にイエスかノーで回答させる場合、その結果を信じるかどうかという問題が出てくる。最終的に人間のチェックに頼る部分が結構増えてしまうこともあります。自動運転車が事故を起こした時、誰が責任を負うのかという問題に似ています。
原:
そう。やはり責任問題があるので、難しくて、まだ結論が出ていない。BIMモデルは時間とともに更新され続けるので、誰がいつチェックするかもなかなか決められないですね。
稲垣:
AIが出した結果に対して、なぜそう判断したのか、というような説明のできないことなども、AIの課題のひとつだと思います。処理の途中でエラーが起きた時、中身をチェックするにはどうしたらいいか、という問題もあります。先ほどご紹介いただいたBIMモデルのチェックでは、直した内容を全部保存しているとおっしゃっていましたが、仮にAI化した時には履歴データを全部残すのは必須なのでしょうね。

マス・カスタマイゼーションが可能になるマンション
中野:
もうひとつ、設計部門でチャレンジしているのは間取りの自動設計です。当初は、間口、奥行きを入力し、スペース内に「リビングの種」、「トイレの種」のようなものを蒔いてやると、お互いに場所取りする感じで間取りが自動生成されるシステムを考えたのですが、箸にも棒にもかからないプランばかりが生成されて、使い物になりませんでした。そこで、過去のプランとの組み合わせで自動生成されるシステムに変えたところ、きれいに収まった効率のよいプランが出てくるようになりました。何らかのルールをロジックとしてシステムに組み込んでおけば、間取りの自動設計はできるのではないかと感じていて、現在は、この方向でシステムを育てている段階です。
稲垣:
なるほど。面白いですね。
中野:
BIMの「見える化」という面ではモデルから直接3DCGを生成し、HMD(Head Mounted Display)を装着してバーチャルな住戸空間内を自由にウォークスルーできるツールを開発済みです。現在でもインテリアのカラーコーディネートを変更したり、部屋からの眺望を変更したりすることができるのですが、将来は家具の配置シミュレーションも含めて、Webブラウザで動くようにしたいと考えています。これと、先ほどの間取り自動生成システムを組み合わせると、お客様が、「水回りは充実させたい」「キッチンは大きい方がいい」といったご要望を入力して間取りをご自身で設計し、完成した間取りで家具の配置をシミュレーションしていただくことが全部Webブラウザでできるようになります。また、気に入った家具やカーテンは即座にECサイトでご購入いただける仕組みを作っておけば、住戸の引き渡し時に注文された商品が全部設置されていて、すぐにお使いいただくこともできます。コストを増やさず柔軟なカスタマイズを行うマス・カスタマイゼーション※4につながってくる話ですが、そうなったら面白いと思っています。

バーチャルな住戸空間内を自由にウォークスルーできるVRシステム。インタリアのカラーコーディネートを変更することも可能
出典:長谷工コーポレーション
原:
BIMと生産システムがつながり、デジタルデータをそのまま工場に流して、ロボットや機械で生産できるようになれば、少量多品種でも規格品と同じ単価で作れるようになるのではないか。技術はまだそこまで追いついていませんが、そういう将来イメージを持っています。
中野:
自動設計のデータが生産システムにそのまま流れるようになると、住戸プランの検討期間を延ばしたり、プラン変更の締切りを後ろにずらしたりすることができるようになります。また、1住戸分の部材を、作る順の逆にトラックに積み込み、現場ではそれを降ろした順に組み立てていくと住戸が完成するというような生産体系も可能になります。
さらに、私の構想、夢をお話しさせていただくと、一つひとつの部材サイズを小さめにしておき、夜な夜なペッパー君みたいなロボットがトラックから部材を降ろして取り付けを行うことが将来可能になれば、ものすごい工期短縮が図れるかもしれません。
原:
少量多品種だけど、プレハブ化されているイメージだよな。
中野:
小さな単位でのプレハブ化手法を裏で構築しておけば、お客様は、間取りからインテリアまで自由に設計できて、住戸が自動的に組み上がる。それができると面白いなと思います。
稲垣:
ありがとうございました。ICT技術が建設業界をどのように変えるのか、我々も気になっていたので、とても興味深い話をお聞きすることができました。次回は、ICT技術が都市や暮らしをどう変えるのかまで話題を広げて、議論していきたいと思います。

※4 マス・カスタマイゼーション:マスプロダクションとカスタマイゼーションの合成語。顧客の要望に応じてカスタマイズされた製品を大量生産と同じ効率で作る仕組み。
次回は、都市や暮らしを変えるICT技術の可能性を中心にお伺いします。乞うご期待!