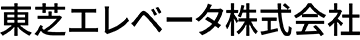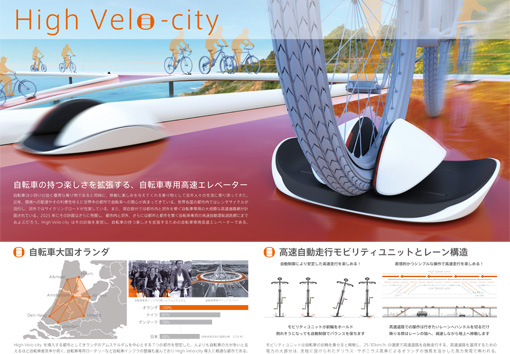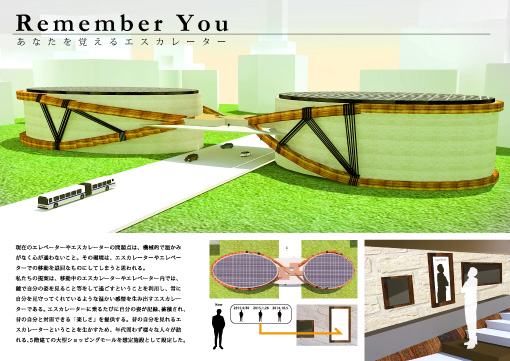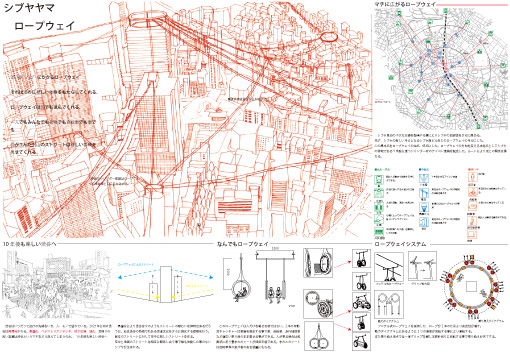第9回(2015年)
未来エレベーター
コンテスト
テーマ
乗って楽しいエレベーター
募集概要
今から10年後の2025年をイメージしながら、利便性を追求したもの、安全性・安心感を追求したもの、乗り心地の良さを追求したもの、都市環境に配慮したもの、プレミアム感のあるものなど、これらのいずれかを踏まえた、これまで誰も見たことがないような「乗って楽しい」エレベーター・エスカレーターを形にしてください。また、提案書のなかには、それが活躍する舞台となるビルや都市も表現してください。
応募資格
大学および大学院、高等専門学校、短期大学、専門学校の在学生。
複数人でチームとして参加する場合、チーム全員が応募対象の条件を満たすものとします。また、各種連絡は電子メールを通して行うため、代表者の方(チームで応募される場合には代表者等最低1名以上の参加者)は、東芝エレベータのWebサイトに接続できるネットワーク環境と、連絡可能な電子メールアドレスが必要となります。
審査員の注目ポイント

今村 創平 氏
建築家、千葉工業大学創造工学部建築学科准教授、アトリエ・イマム主宰
エレベーターがこの世に生まれた頃、それは夢の発明でした。エレベーターが普及し始めた頃、百貨店のエレベーターガールは憧れの職業でした。エレベーターの性能は飛躍的に向上しましたが、それは今日も夢の乗り物でしょうか。エレベーターが、その栄光の日々を取り戻すことはあるのでしょうか。
一日何度も乗るのですから、エレベーターに関わる時間を楽しくできないか。もしくは、例えばエレベーターがエネルギーを生み出せれば、乗ることが楽しみになるかもしれません。会社のエレベーターに毎日乗るのであれば、体調管理のデータを取るとか。エレベーターは、規格によりどれも同じようなものですが、特別なシチュエーション用のエレベーターはどうでしょうか。結婚式用とか、雪山スキー場用とか。または、オンリーワンのエレベーター。
これまでになかったような、そのアイデアを聞くだけで楽しくなってしまうような、そんなエレベーターの提案を期待しています。
IMAMURA Souhei●建築家。千葉工業大学創造工学部建築学科准教授。1966年東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。AAスクール(ロンドン)、長谷川逸子・建築計画工房(株)を経て2002年(有)アトリエ・イマム一級建築士事務所設立。ブリティッシュ・コロンビア大学大学院兼任教授を経て現職。東京大学大学院、芝浦工業大学大学院などにて非常勤講師を務める。主な建築作品に「オーストラリア・ハウス」「神宮前の住宅」、「大井町の集合住宅」。著書は『現代都市理論講義』(オーム社、2013)、『日本インテリアデザイン史』(共著、オーム社、2013)など。訳書として『20世紀建築の発明』(鹿島出版会、2012)。
Webサイト[ATELIER IMAMU]: http://www.atelierimamu.com/

谷口 守 氏
筑波大学システム情報系社会工学域教授
生まれて最初にエレベーターに乗った時のことを覚えていますか? 昔のエレベーターは今と違い、動き出す時や止まる時に大きな加速度を感じました。私はそれが楽しくて、デパートのエレベーターに何度も乗り降りして遊ぼうとした記憶があります。何を楽しく思うかは人それぞれで、そのような楽しさの種はいろんな所に隠れているものです。それをどう引き出して育てるか、皆さんのユニークな創造性を期待しています。
また、「移動すること」は、まちで暮らすうえで誰もが行う、基本的できわめて重要な「行為」です。その移動を支えるエレベーターが今までにない楽しい移動手段へと進化することで、建物やまち全体にも大きな変革が生まれます。最近では人口減少や高齢化などによって、多くのまちで賑わいが損なわれつつあります。新たな楽しいエレベーターが核となって空間全体に新たな価値が生み出され、まち自体が生まれ変わるような影響力を持った提案を期待します。
TANIGUCHI Mamoru●1961年生まれ。京都大学大学院工学研究科博士後期課程 単位修得退学。工学博士。京都大学工学部助手、カリフォルニア大学客員研究員、岡山大学環境理工学部教授などを経て、2009年より現職。
IFHP(International Federation for Housing and Planning)評議員、日本都市計画学会 理事、国土交通省 社会資本整備審議会 専門委員、環境省 中央環境審議会 専門委員、つくば市 公共空間活用検討委員会 委員長などを歴任。著書に『入門 都市計画』(森北出版)などがある。
Webサイト[筑波大学 システム情報系 近未来計画学研究室]: http://infoshako.sk.tsukuba.ac.jp/~tj330/Labo/taniguchi/

小川 克彦氏
慶應義塾大学 環境情報学部 教授
現在のエレベーターやエスカレーターは、昔と比べると機能もデザインも大きく進化していますから、「乗って楽しいエレベーター」を実現するためには、利用者の視点からエレベーターやエスカレーターを見直してみることが効果的ではないでしょうか。その際、キーワードは3つあると思います。
1つめはエレベーターを使う時の「文脈」です。例えば、エレベーターを利用する会社の個性に合わせてメッセージを発するようなエレベーターがあったら楽しいでしょう。
2つめは、利用者がエレベーターに乗った時に得られる経験や満足について考えるユーザーの「経験(エクスペリエンス)」です。忘れられない思い出になるエレベーターや、気分転換のできるエレベーターはないものか、と夢が膨らみます。
最後に触れておきたいのは「安心」です。もちろんメーカー各社は利用者の安全や安心を大前提に考えていると思いますが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックには多くの外国人も訪れることを考慮して、世界中の人々が安心できる視点から考えた作品についても期待しています。
OGAWA Katsuhiko●1978年、慶應義塾大学 工学研究科 修士課程修了。同年、日本電信電話(株)に入社。画像通信システムの実用化、インターフェースデザインやウェアラブルシステムの研究、ブロードバンドサービスや端末の開発、R&D戦略の策定に従事。NTTサイバーソリューション研究所所長を経て、2007年より現職。工学博士。専門は、ヒューマンインターフェース、コミュニケーションデザイン、メディアデザインなど。
著書に『恋愛のアーキテクチャ』(共著、青弓社)、『つながり進化論─ネット世代はなぜリア充を求めるのか』(中公新書)、『デジタルな生活─ITがデザインする空間と意識』(NTT出版)などがある。
Webサイト[balab | 小川克彦研究室]: http://www.balab.jp/

KIKI 氏
モデル
エレベーターに乗り込むとき、また降りるとき、ある時期までドキドキしていました。それは何か良いことを期待するものではなく、何か良からぬことが起きるのではないかという漠然とした不安から生じるドキドキでした。
ところがあるとき、これまでとは違うドキドキを味わいました。高層ビルの階上にある展望台に行くためのエレベーターに乗ったときのことです。照明による演出がなされているエレベーターのかごに乗ったときから、特別な空間へ連れていってくれるような感覚に導かれ、降りるときにはすでに異次元にたどり着いた気分になっていました。そのドキドキは、ワクワクに近いものでした。
ほんの少しの時間で、人の心に変化を与えることができる。それは照明に限らず、何かとても小さなことで、日常のなかで得られる些細なきっかけかもしれません。エレベーターを通過点として、ワクワクとした、楽しい期待を抱かせる何かに、出会えることを楽しみにしています。
KIKI●東京都出身。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒。 雑誌をはじめ広告、TV出演、連載の執筆、近年では自身の写真展「PRISMA」シリーズを発表。また、芸術祭に作家として参加するなど活躍の幅を広げている。NTV『ゆっくり私時間 ~my weekend house~』レギュラー出演中。 著書に『山が大好きになる練習帖』(雷鳥社)、『美しい山を旅して』(平凡社)、スタイルブック『KIKI LOVE FASHION』(宝島社)など多数。
Webサイト [Facebook]:http://www.facebook.com/pages/KIKI/238880896195077

藤田 善昭
東芝エレベータ株式会社 常務 統括技師長
エレベーターは重要な社会インフラのひとつとして、建物の高層化・多様化とともにさまざまな進化を遂げてきました。これまでは、主に安全・安心・快適を提供する移動手段として機能する一方、高速化や大容量化、静粛性能の向上などを実現しています。
今回のテーマ「乗って楽しいエレベーター」では、新たに「乗る楽しさ」という視点に注目し、思わず乗ってみたくなる近未来のエレベーター・エスカレーターについての幅広いアイデアを募集します。
このテーマは、東芝グループが掲げる「『モノ』から『モノ+こと』へ」というコンセプトにもつながります。よりよい「モノ」をお客様に提供するモノづくりの会社から、「モノ」に加えて「こと」も提供する会社になる──モノを使って何をするのかという点も追求していくという意味合いです。既存のエレベーター・エスカレーターの概念を超えた、近未来の社会をより一層豊かにする斬新なアイデアが寄せられることを大いに期待しています。
FUJITA Yoshiaki●1959年生まれ。東京大学工学部卒業。
東芝エレベータ株式会社 技術本部開発部長、エレベーター担当技師長、技術本部長を経て、現在に至る。