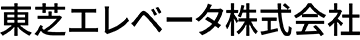左から舞台美術家の浅香正廣さんと弟子の小島芽唯さん。この日は音楽フェスの舞台製作スタッフの皆さんも集まり賑やかな浅香さんのアトリエ。
写真:阿部了 文:阿部直美
古い酒蔵を改装してつくられた「深谷シネマ」。
“我が街に映画館を”、というひとりの男のロマンが、市民を巻き込んで生まれた映画館だ。
ここには、今では珍しい手描きの「看板絵」が掲げられている。
看板絵の絵師・浅香正廣さん、そして映画館の発起人・竹石研二さんに会いに行った。

映画館の正面、東蔵の前に上映中の看板絵を掲げている。この日は、浅香さんの仕事仲間でもある庄子理沙さんが描いたものが並んでいた。
埼玉県深谷市の「深谷シネマ」は、江戸元禄創業の造り酒屋「七ツ梅酒造」の跡地にある。酒蔵を改装した映画館はそれだけでも珍しいのだが、何と毎回手描きの看板絵が掲げられている映画館なのだ。館長の小林俊道さんも、その看板絵を楽しみにしているひとり。
「絵師の浅香さんは、いつもふらりとやって来て、特に何も言わず、“ん”って描いた絵を受け付けの台に置いていかれるんです。“よろしくね”、みたいな感じで。それで、映画を一本観ていかれます」。看板絵は畳一畳ほどのサイズだが、布に描くので折りたたんで手渡される。「今回はどの映画かなって、わくわくしながら布を広げるんですよ。というのも、うちが映画を指定して描いてもらっているんじゃないんです。看板絵は浅香さんのご厚意。ボランティアで描いてくださっているんですよ」と小林さん。

館長の小林俊道さん。フィルム映写機もあるが、現在はデジタルが主流。毎回アンケートでお客さんの声を聞いて、上映作品を決めている。
ボランティアの看板絵師? 浅香さんとは、どんな人だろう。小林さん曰く、「あまりご自分のことを話さないので、実は本業のことも詳しくなくて…」とのこと。どこかヴェールに包まれた存在の浅香さんに会いたくて、さっそく深谷シネマから車で30分ほどの寄居町にあるアトリエを訪ねることにした。
山の斜面の、すぐ脇が雑木林という場所に浅香さんのアトリエはあった。体育館のような広い空間に、制作途中だった音楽フェスティバルの舞台絵が床一面に広げてある。浅香正廣さん、御年79歳。現役の舞台美術家だ。

浅香正廣さん
Masahiro Asaka
「この夏は本業が忙しくて、なかなか看板絵が描けないんだ」と浅香さん。最近では深谷シネマの看板絵を見た他の映画館からの依頼も。

「テレビ、芝居、イベント、壁画、絵に関するものなら何でもやってきましたよ。コンサートの舞台もいっぱいやってきた。うーん、名前が出てこない。そうだ、アルフィー、ユーミン、サザン、松田聖子、氷川きよし……」。棚からアルバムを引っ張り出してきて、手掛けた舞台の写真を見せてくれる。「テレビだったら、ベストテンって歌番組あったよね。ドリフの番組もやったな。コントやる時に、海とか山とかの場面が出てくるでしょ。あの頃は、バックに絵を飾っていたんだ。僕らは背景屋さんって言われたね」。懐かしい番組名を言われて、記憶がよみがえってくる。背景は手描きの絵だったのか、と今さらながら思う。

神奈川県川崎市生まれの浅香さんは、中学を卒業後に電気工場に就職。「子どもの頃から絵が好きだったけど、当時は美大に行くとか絵の仕事をするとか、そんな選択肢はなかったからね」。5年勤めた後に自動車工場に転職した。海外渡航が一般的ではなかった時代、転職先には海外渡航の経験者が何人もいて若かった浅香さんを刺激した。その会社を3年で辞め、稼いだお金を持ってヨーロッパへ行く決心をする。「とにかくあちこちをスケッチして絵を描くのが夢だったからね。横浜から船でナホトカ港に行って、その後はシベリア鉄道。スペインのマドリッドに長く滞在しました。研究所に入って絵のデッサンを勉強したの。安ペンションで、1年半くらい向こうにいたかなあ」。そして照れ臭そうに、「実はさ、家内も一緒に行ったの」と付け加えた。
帰国後、公共職業安定所(ハローワーク)で「大道具」の仕事を見つけた。テレビ番組の舞台造りだ。「でも、絵の学校を出てないから、なかなか描かせてもらえなかったの。そのうち現場がどんどん忙しくなって、『浅香描いてみろっ』て言われて、そっからだね」。1989年に独立し、自分のアトリエを構えた。ずっと第一線で活躍してきた浅香さんが、なぜ映画の看板絵なんだろう。

床一面に型紙を広げ、バランスを見る浅香さんとスタッフの皆さん。音楽フェスのために10枚以上を仕上げる予定で、真夏のアトリエで汗だくだ。
「あらゆる仕事をやってきたけど、映画の看板絵だけはやってなかったんですよ。看板屋さんっていう専門の職業の人がいたからね。でもずっと憧れてて、いつかやってみたいなあと思ってたんです。10年くらい前、深谷シネマへ行って、描かせてくださいって当時の館長の竹石さんに言ってみたの。自分の勉強にもなるし、シネマにとってもいいかなと思って。看板屋さんはね、映画のちらしをそのまま幻灯機で映してなぞって描くんです。それじゃあ面白くないから、僕はデッサンからやる。好きに描かせてもらってるんですよ」

「人物は特に難しい」と弟子の小島さん。普段はタブレットで絵を描くので、大きな看板絵を描くにあたって浅香さんからアタリのつけ方などを教わった。
この10年で300枚以上を手掛けてきたことになる。3年前には小島芽唯さんという弟子もできた。小島さんは、中学2年の時に工房で浅香さんから描き方を教わって看板絵デビュー。これまでに7作品を描いてきた。今は高校1年で、将来はアニメーターになりたいという夢がある。現在は小島さんの他にも3人、浅香さんの仕事仲間が深谷シネマの看板絵を描いている。若手にぜひ頑張ってほしい、という浅香さんの思いがあるのだ。
さて、ここでもうひとり、深谷シネマを語る上でなくてはならない人がいる。映画館の立ち上げから、幾多の困難を乗り越えて深谷シネマを引っ張ってきた竹石研二さんだ。昨年4月に館長の座を小林さんに譲った後も、映画館を特別な思いで見守っている。

深谷シネマの発起人で現在は名誉館長の竹石研二さん。布に描かれた看板絵は、すべて折りたたんで保管してある。
竹石さんは、1975年に開校した「横浜放送映画専門学院」(現 日本映画大学)の1期生。今村昌平監督が若い映画人を育てる目的で作った学校だ。当時の竹石さんはすでに20代半ばで、在学中には2人目の子どもが誕生。看護士の妻の応援あっての学生生活だった。卒業後は10年近く児童映画に関わった。その後、妻の出身地・深谷市でサラリーマン生活を送り映画とは離れていたが、50歳の時、我が街に映画館を作ろうと決意する。商店街に空き店舗が目立っていたため、好きな映画で町おこしをしたい、という思いもあった。
ある日、たまたま出会った年配の女性に「何の映画が観たい?」と聞くと、「そりゃあ、愛染かつらだよ」と返ってきた。さっそく竹石さんは、元用品店を改装して60席の仮設の映画館を作った。最前列は畳と座椅子、その後ろは喫茶店主が提供してくれたローチェア、さらに後ろはパイプ椅子という映画館だ。『愛染かつら』を上映すると、70歳以上のご婦人らがぞくぞくと詰めかけ、2週間で1,150人の集客となった。お年寄りたちは、上映の後も帰らない。お茶とたくあんでお喋りに花が咲いて、それはもう楽しそうだった。

竹石さんが、しみじみとあの日を振り返る。「あるおばあちゃんはね、その昔若くて奉公に出ていた頃、休みの日に街で『愛染かつら』の映画看板を見たんだって。映画を観たいなあと思いながら、その時は結局観られなかったらしいんだ。“今日ようやく観られました”なんて言われて感激したよ」。竹石さんにとって、映画の力をまざまざと見せられた体験だった。その後、NPO法人の立ち上げなどを経て、2002年に「深谷シネマ」が誕生。区画整理で2度の移転を余儀なくされたが、助成金や深谷市民からの寄付もあり何とか乗り切ってきた。「映画だから、できたんですよ」という竹石さんの言葉は、実感がこもっていて重い。
我が町に映画館を、という情熱で走り続けてきた竹石さん。一方の浅香さんは、看板絵を描きたいという純粋な思いで深谷シネマの扉をたたいた。映画の周りにいる人たちの人生もまた、熱くドラマチックだ。映画とは、そういう人たちを呼びよせるものなのかもしれない。その背中を見てきた若い世代は、どんなふうにこれから深谷シネマと関わっていくのだろう。この先も楽しみだ。
【深谷シネマ】

〒366-0825 埼玉県深谷市深谷町9-12
TEL 048-551-4592
毎週火曜休館
300年の歴史を持つ「七ツ梅酒造」跡地には、深谷シネマの他に古書店や珈琲店、洋服屋などが趣のある建物を生かして営業中。
一帯が、魅力的な空間になっている。映画のロケ地としても利用されています。